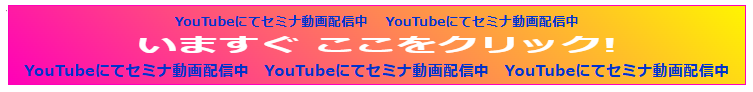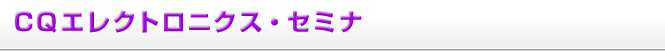●〆切迫る!動画をチェック
画像を"クリック"すると動画が見られます!

【開催日】2026年1月30日(金)
★実習・はじめてのFPGA設計入門【Tang Nano 9K / Kiwi 1P5 +学習ベースボード付き…割引プランあり】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0123

【開催日】2026年2月3日(火)
★初めてのアナログ回路設計講座:高精度A/D変換の極意(その1)【オンライン同時開催セミナ】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0126

【開催日】2026年2月4日(水)
★初めてのアナログ回路設計講座:高精度A/D変換の極意(その2)【オンライン同時開催セミナ】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0127

【開催日】2026年2月5日(木) ~6日(金)
★実習・アナログ・フィルタ回路設計 基礎の基礎
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0128

【開催日】2026年2月9日(月)
★装置におけるシールド/グラウンド設計法 [参考書籍付き]【オンライン限定セミナ】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0142

【開催日】2026年2月10日(火)
★手ぶらでOK!実習・マイコン通信インターフェースの使い方「超」入門【後閑 講師設計のオリジナル教材基板付き】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0134

【開催日】2026年2月13日(金)
★特別KIT付き★ 手ぶらでOK!実習・小型Linuxボードと無線LANモジュールを使ったWi-Fi開発の始め方
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0042
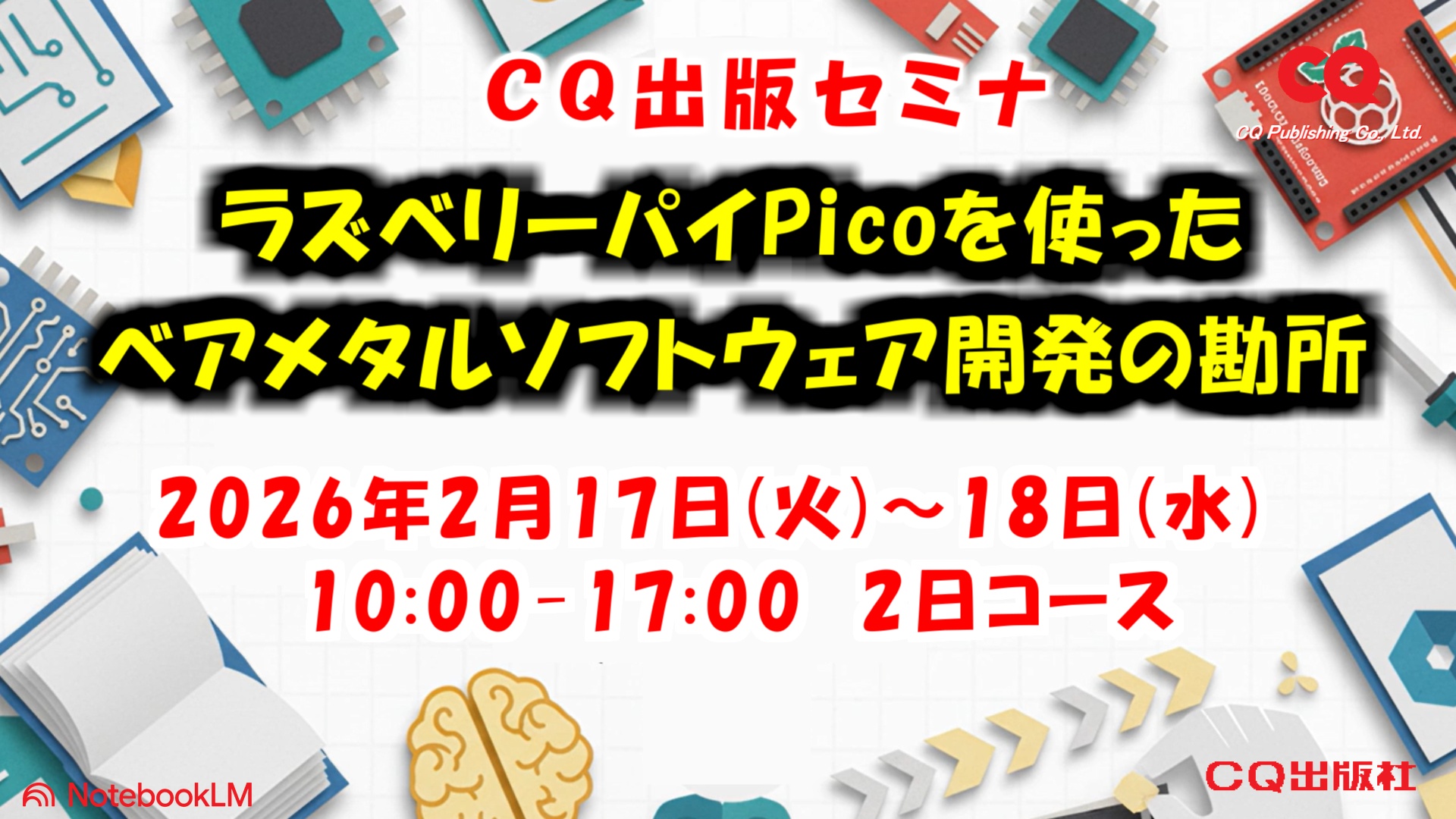
【開催日】2026年2月17日(火) ~ 18日(水)
★ラズベリーパイPicoを使ったベアメタルソフトウェア開発の勘所【実習キット付き】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0130

【開催日】2026年2月20日(金)
★カラー時計で学ぶMicroPython【オリジナル教材基板付き】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0130

【開催日】2026年2月24日(火)
★基礎から理解するディジタル・フィルタ入門
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0143

【開催日】2026年3月24日(火)
★LLMビギナ大歓迎!実習・ラズパイでローカルLLMを動かして生成AIのアプリを作ってみる実験【生成AI有償版期限付き使用権付き】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0148

【開催日】2026年2月27日(金)
★各種二次電池充電回路入門[講師実演付き]【オンライン同時開催セミナ】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0131

【開催日】2026年3月3日(火)
★手ぶらでOK!実習・組み込みリアルタイムOS FreeRTOS「超」入門【後閑 講師設計のオリジナル教材基板付き】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0135