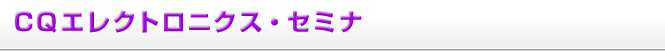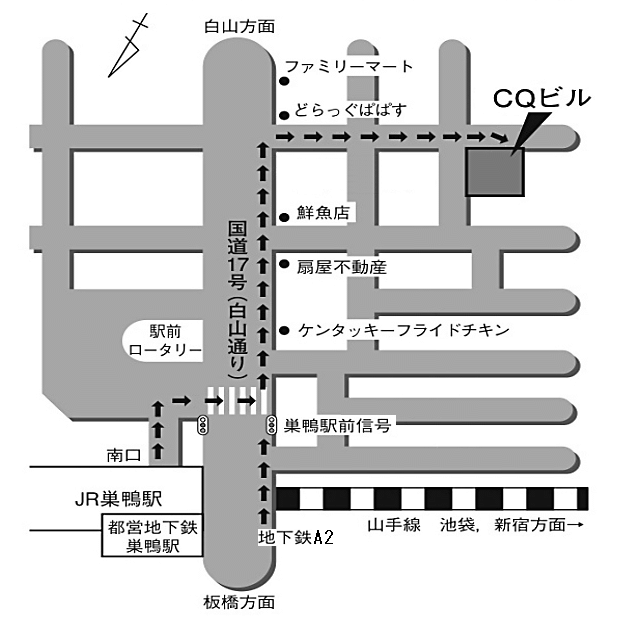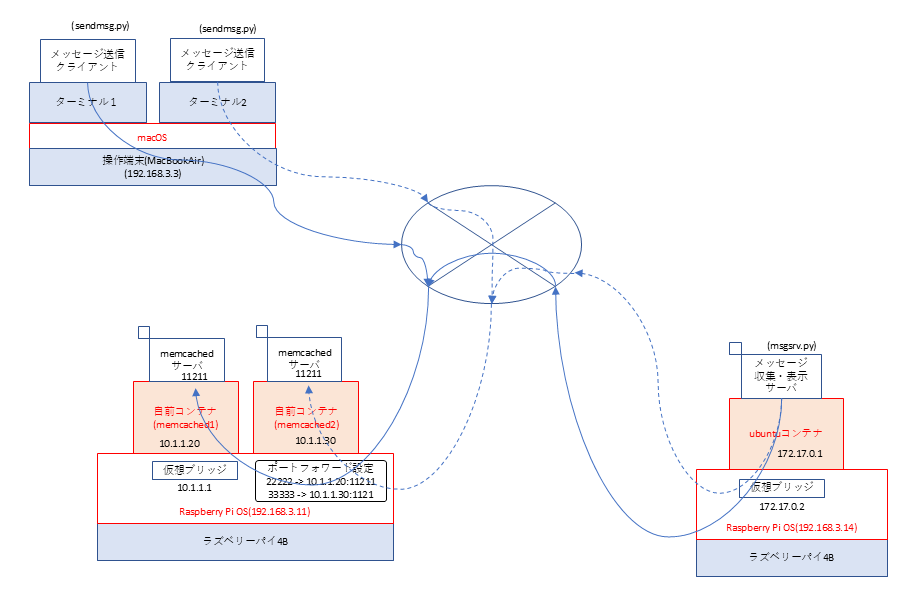●〆切迫る!動画をチェック
画像を"クリック"すると動画が見られます!
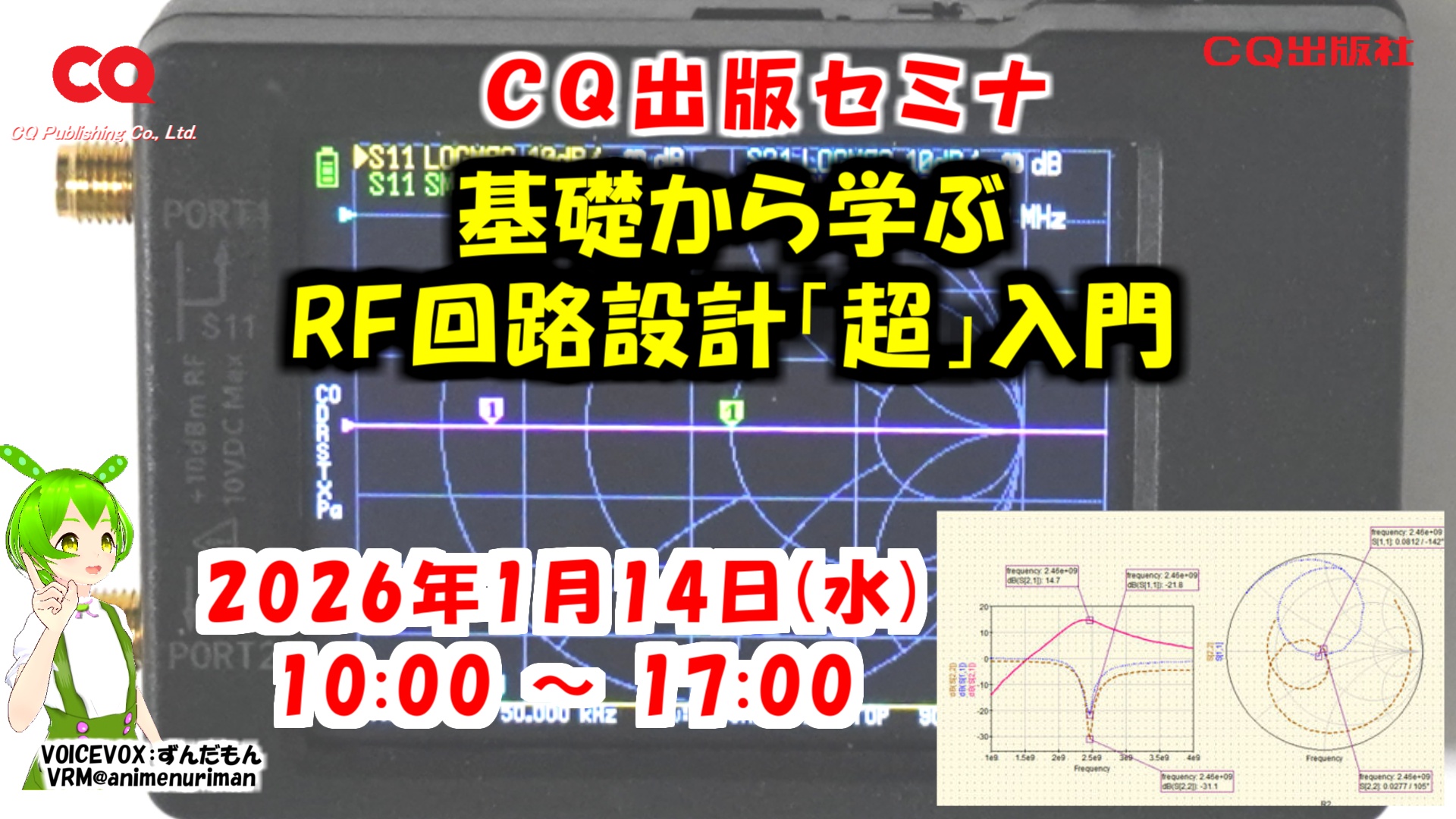
【開催日】2026年1月14日(水)
★実習・基礎から学ぶRF回路設計「超」入門
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0115

【開催日】2026年1月16日(金)
★実習・1日でわかる!CANプログラミング入門
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0103

【開催日】2026年1月20日(火)
★ビギナ大歓迎!実習・ChatGPTとRaspberry Pi AIカメラでアプリケーションを作ってみる練習【ラズパイAIカメラ&生成AI有償版期限付き使用権付き】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0125

【開催日】2026年1月25日(日)
★半導体ESD設計入門
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0117

【開催日】2026年1月26日(月)
★徹底解説!高速ビデオ・インターフェースの最新動向【オンライン限定セミナ】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0132
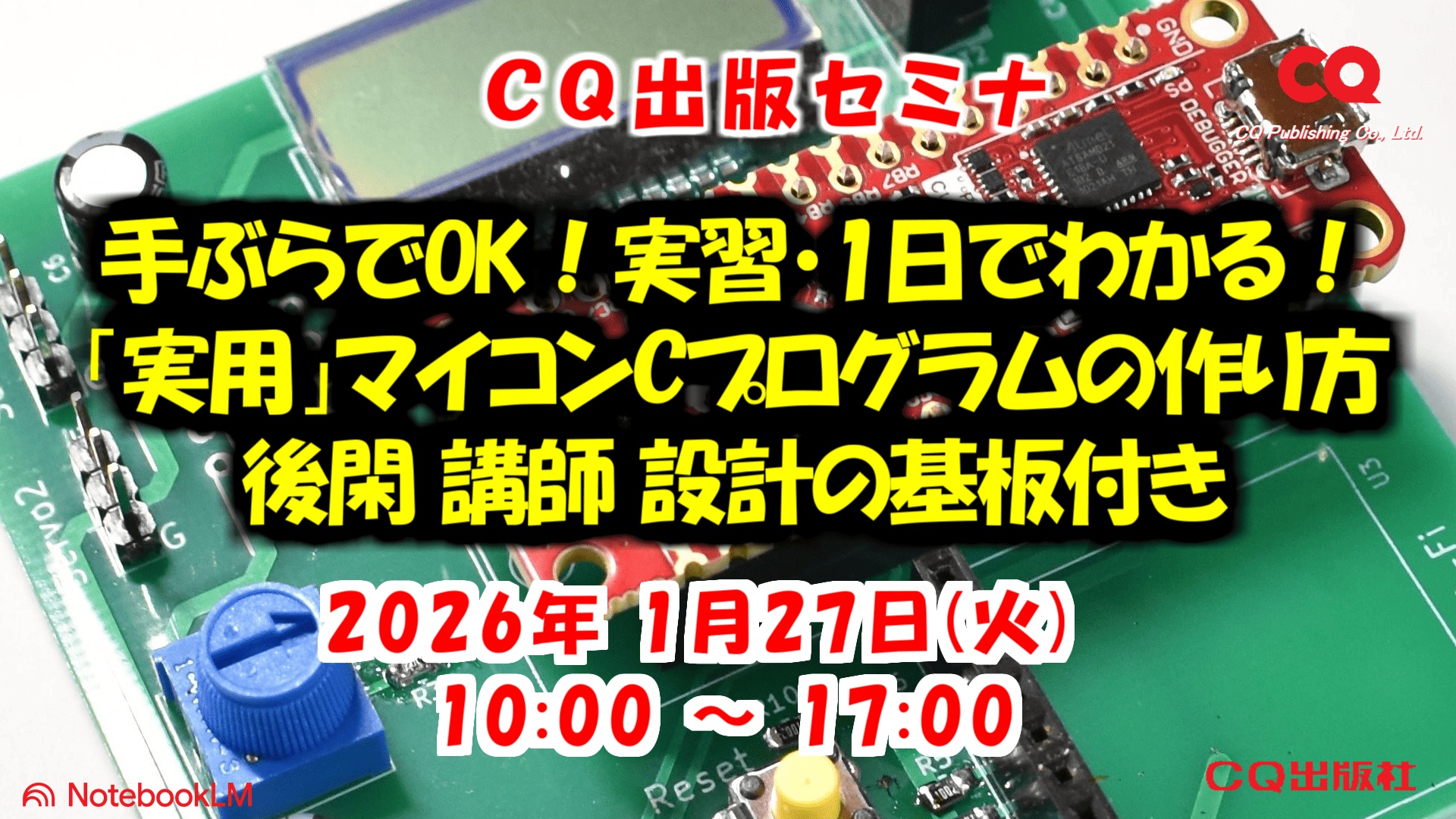
【開催日】2026年1月27日(火)
★手ぶらでOK!実習・1日でわかる!「実用」マイコンCプログラムの作り方~ビギナ応援企画【後閑 講師設計のオリジナル教材基板付き】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0133

【開催日】2026年1月28日(水)
★実習・ギガビット高速信号伝送技術の基礎と適用技術および評価
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0120

【開催日】2026年1月30日(金)
★実習・はじめてのFPGA設計入門【Tang Nano 9K / Kiwi 1P5 +学習ベースボード付き…割引プランあり】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0123

【開催日】2026年2月3日(火)
★初めてのアナログ回路設計講座:高精度A/D変換の極意(その1)【オンライン同時開催セミナ】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0126

【開催日】2026年2月4日(水)
★初めてのアナログ回路設計講座:高精度A/D変換の極意(その2)【オンライン同時開催セミナ】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0127

【開催日】2026年2月5日(木) ~6日(金)
★実習・アナログ・フィルタ回路設計 基礎の基礎
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0128

【開催日】2026年2月9日(月)
★装置におけるシールド/グラウンド設計法 [参考書籍付き]【オンライン限定セミナ】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0142

【開催日】2026年2月10日(火)
★手ぶらでOK!実習・マイコン通信インターフェースの使い方「超」入門【後閑 講師設計のオリジナル教材基板付き】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0134

【開催日】2026年2月13日(金)
★特別KIT付き★ 手ぶらでOK!実習・小型Linuxボードと無線LANモジュールを使ったWi-Fi開発の始め方
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0042
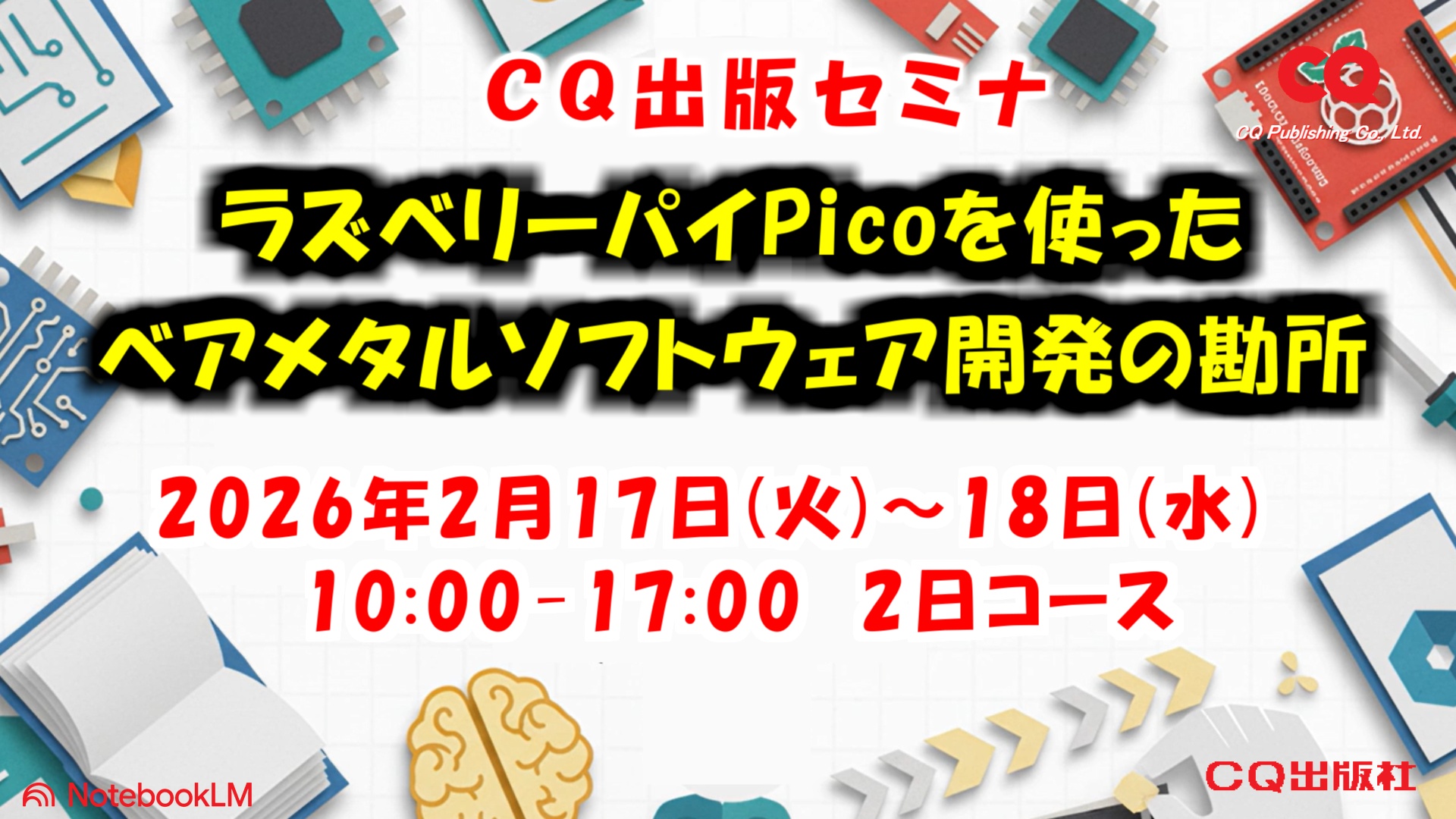
【開催日】2026年2月17日(火) ~ 18日(水)
★実習・ラズベリーパイPicoを使ったベアメタルソフトウェア開発の勘所【実習キット付き】
https://seminar.cqpub.co.jp/ccm/ES25-0129