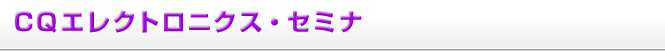
実習・正しい波形を測定するためのオシロスコープの使い方
実習・正しい波形を測定するためのオシロスコープの使い方
|
|
【開催日】2016年2月10日(水) 10:00-17:00 1日コース
【セミナNo.】ES15-0156 【受講料】21,000円(税込)
【会場】東京・巣鴨 CQ出版社セミナ・ルーム [地図]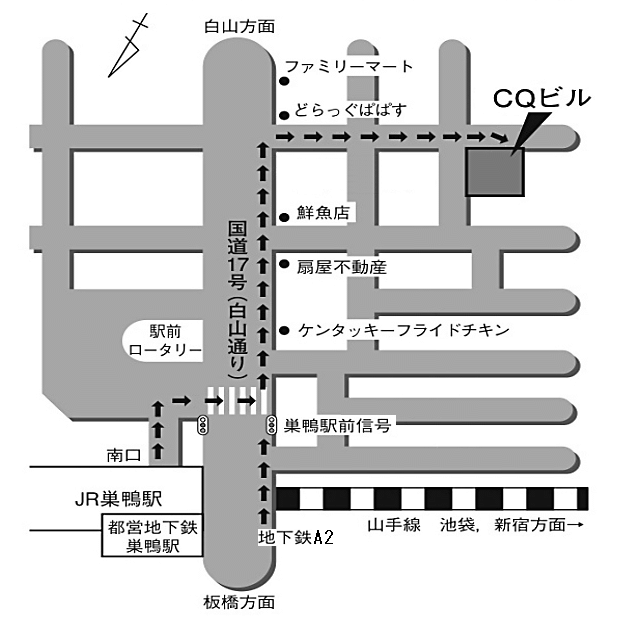
【セミナNo.】ES15-0156 【受講料】21,000円(税込)
【会場】東京・巣鴨 CQ出版社セミナ・ルーム [地図]
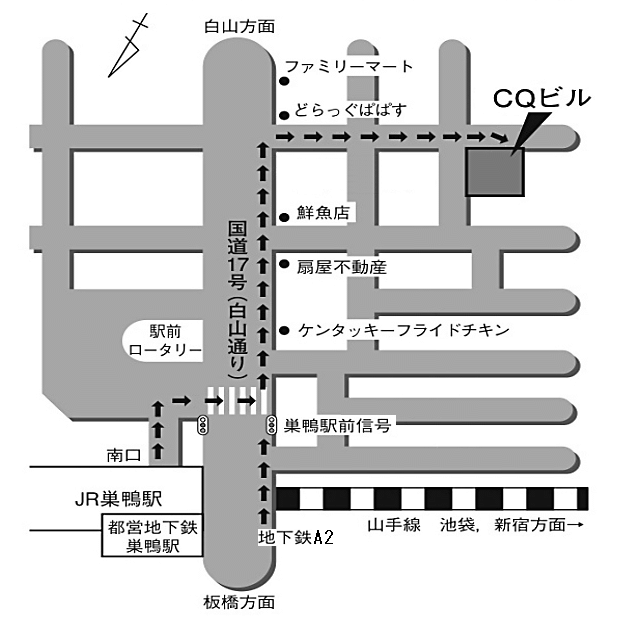
ディジタル・マルチメータや周波数カウンタなどは,「数値」で測定結果が表示される.適切な性能の機器を選択すれば,誰が測っても測定結果は同じある.しかし,「波形」を表示・観測するオシロスコープは,測定者によって測定結果にばらつきが出る場合がある.
波形を測定する場合は,適切な性能のオシロスコープを選ぶだけでなく,パラメータに合わせて電圧軸や時間軸を設定する必要がある.表示レンジを自動調整する「オートセット」という機能があるが,波形形状によっては適切に働かないことがある.さらに,プローブを適切に使用するスキルも必要である.プローブは場合によっては元の信号をひずませたり,ノイズを拾ってしまったり,極端な場合は装置の動作に影響を与えてしまうことがある.
セミナでは,測定に必要になるオシロスコープの基本知識を習得した上で,プロービングにより発生するさまざま問題と解決策を解説する.さらに,パワー・エレクトロニクスや高速ディジタル信号における測定の諸問題と解決のヒントも説明する.
※実習では,「高周波プローブ」,「近磁界ノイズを検出できるプローブ」,「電源の高周波リプルの検出できるプローブ」のうち,一つを手作りします.製作したプローブは持ち帰ることができます.
波形を測定する場合は,適切な性能のオシロスコープを選ぶだけでなく,パラメータに合わせて電圧軸や時間軸を設定する必要がある.表示レンジを自動調整する「オートセット」という機能があるが,波形形状によっては適切に働かないことがある.さらに,プローブを適切に使用するスキルも必要である.プローブは場合によっては元の信号をひずませたり,ノイズを拾ってしまったり,極端な場合は装置の動作に影響を与えてしまうことがある.
セミナでは,測定に必要になるオシロスコープの基本知識を習得した上で,プロービングにより発生するさまざま問題と解決策を解説する.さらに,パワー・エレクトロニクスや高速ディジタル信号における測定の諸問題と解決のヒントも説明する.
※実習では,「高周波プローブ」,「近磁界ノイズを検出できるプローブ」,「電源の高周波リプルの検出できるプローブ」のうち,一つを手作りします.製作したプローブは持ち帰ることができます.
1.オシロの選び方①必要な周波数帯域は何MHz?
高周波信号用の測定器としてオシロスコープとスペクトラム・アナライザがあげられる.両者の原理を理解しながら,測定できる周波数範囲を理解する.さらに測定する機会の多いパルス信号を最小のひずみで測定するために必要な周波数帯域について考察する.これにより適切な過不足ない性能のオシロスコープを選ぶことができる.
2.オシロの選び方②必要なサンプル・レートとレコード長はいくつ?
現在ではオシロスコープと言えば,ディジタル・オシロスコープである.ディジタル・オシロスコープで周波数帯域と同じくらい大切な性能が「サンプリング・レート」と「レコード長」である.どちらも測定したい信号に対して最適の設定値がある.
ここでは「信号-周波数帯域-サンプリング・レート-レコード長」の最適設定について理解を深める.また,ノイズを低減できるアベレージ取り込みの効果や注意点についても説明する.
3.なぜプローブは10:1なのか?
信号のピックアップには欠かせないプローブだが,意外と信号への影響は少なくない.ここでは基本の10:1プローブがなぜ10:1なのか?を原理から解説する.
4.ひずみを最小限に抑えるプロービング・テクニック
波形のひずみを最小に抑える理想的なプロービングと現実とは大きな差がある.実用性を保持したまま,ひずみを最小限度に抑えるテクニックについて説明する.さらに,より真実に近い結果が得られるアクティブ・プローブの動作を説明する.
5.パワー・エレクトロニクスの波形測定におけるプローブの問題点
パワー・エレクトロニクスの測定では安全性を確保しつつ,グラウンドを浮かした測定をしなければならない.ここでは「壁コンセントの向こう側」がどうなっているのか,高電圧プローブの隠れた問題点,電流プローブの隠れた問題点,さらにスイッチング波形観測での誤差を抑える方法について説明する.
【製作実習】約500円で自作できるプローブにトライ!
「高周波プローブ」,「近磁界ノイズを検出できるプローブ」,「電源の高周波リップルの検出できるプローブ」のうち,一つを製作する.

実習で製作するプローブその1「Z0改良型高周波プローブ」

実習で製作するプローブその2「電源の高周波リップルの検出できるプローブ」

実習で製作するプローブその3「近磁界ノイズを検出できるプローブ」
●対象聴講者
・日頃からオシロスコープを使用しているが,「習うより慣れろ」で使っている方
・操作方法はマニュアルを参照すれば良いが,マニュアルには記載されていないテクニックを身につけたい方
●講演の目標
・自信を持ってオシロスコープとプローブを選択し,適切なプローブの接続,オシロスコープの設定を行うことで,再現性の高い波形計測を行えるようになる(特に,製品のデータシートに波形データを添付する場合,そのデータには大きな責任があり,不適切なデータではクレームの対象になる可能性がある.)
・過不足のない計測器を選ぶスキルを持つことで,有効な設備投資が可能になる
●参考文献
天野 典 著;「ディジタル・オシロスコープ実践活用法」 2010年5月,CQ出版.
高周波信号用の測定器としてオシロスコープとスペクトラム・アナライザがあげられる.両者の原理を理解しながら,測定できる周波数範囲を理解する.さらに測定する機会の多いパルス信号を最小のひずみで測定するために必要な周波数帯域について考察する.これにより適切な過不足ない性能のオシロスコープを選ぶことができる.
2.オシロの選び方②必要なサンプル・レートとレコード長はいくつ?
現在ではオシロスコープと言えば,ディジタル・オシロスコープである.ディジタル・オシロスコープで周波数帯域と同じくらい大切な性能が「サンプリング・レート」と「レコード長」である.どちらも測定したい信号に対して最適の設定値がある.
ここでは「信号-周波数帯域-サンプリング・レート-レコード長」の最適設定について理解を深める.また,ノイズを低減できるアベレージ取り込みの効果や注意点についても説明する.
3.なぜプローブは10:1なのか?
信号のピックアップには欠かせないプローブだが,意外と信号への影響は少なくない.ここでは基本の10:1プローブがなぜ10:1なのか?を原理から解説する.
4.ひずみを最小限に抑えるプロービング・テクニック
波形のひずみを最小に抑える理想的なプロービングと現実とは大きな差がある.実用性を保持したまま,ひずみを最小限度に抑えるテクニックについて説明する.さらに,より真実に近い結果が得られるアクティブ・プローブの動作を説明する.
5.パワー・エレクトロニクスの波形測定におけるプローブの問題点
パワー・エレクトロニクスの測定では安全性を確保しつつ,グラウンドを浮かした測定をしなければならない.ここでは「壁コンセントの向こう側」がどうなっているのか,高電圧プローブの隠れた問題点,電流プローブの隠れた問題点,さらにスイッチング波形観測での誤差を抑える方法について説明する.
【製作実習】約500円で自作できるプローブにトライ!
「高周波プローブ」,「近磁界ノイズを検出できるプローブ」,「電源の高周波リップルの検出できるプローブ」のうち,一つを製作する.

実習で製作するプローブその1「Z0改良型高周波プローブ」

実習で製作するプローブその2「電源の高周波リップルの検出できるプローブ」

実習で製作するプローブその3「近磁界ノイズを検出できるプローブ」
●対象聴講者
・日頃からオシロスコープを使用しているが,「習うより慣れろ」で使っている方
・操作方法はマニュアルを参照すれば良いが,マニュアルには記載されていないテクニックを身につけたい方
●講演の目標
・自信を持ってオシロスコープとプローブを選択し,適切なプローブの接続,オシロスコープの設定を行うことで,再現性の高い波形計測を行えるようになる(特に,製品のデータシートに波形データを添付する場合,そのデータには大きな責任があり,不適切なデータではクレームの対象になる可能性がある.)
・過不足のない計測器を選ぶスキルを持つことで,有効な設備投資が可能になる
●参考文献
天野 典 著;「ディジタル・オシロスコープ実践活用法」 2010年5月,CQ出版.