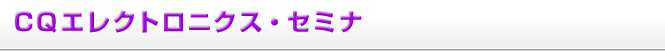
高速ビデオ・インターフェース/HDMI2.0a, DP1.3, eDP1.4aの徹底解説![講師による実験実演付き]
高速ビデオ・インターフェース/HDMI2.0a, DP1.3, eDP1.4aの徹底解説![講師による実験実演付き]
|
|
【開催日】2015年9月10日(木) 10:00-17:00 1日コース
【セミナNo.】ES15-0083 【受講料】18,000円(税込)
【会場】テクトロニクス社 セミナールーム [地図]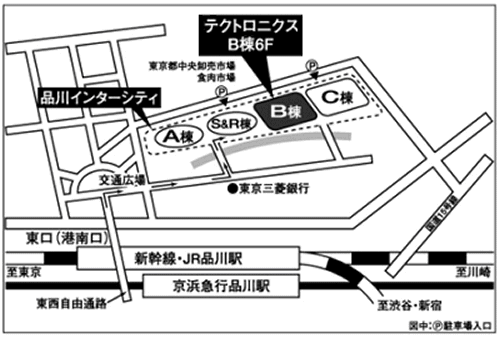
【セミナNo.】ES15-0083 【受講料】18,000円(税込)
【会場】テクトロニクス社 セミナールーム [地図]
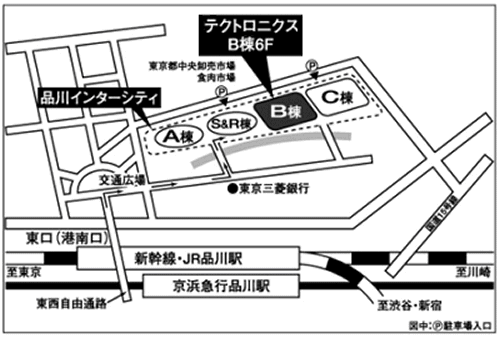
薄型テレビやDVDレコーダなど,ディジタル家電機器の主力AVインターフェースの地位を築いたHDMIは,2013/9にバージョン2.0,2015/4に2.0aをリリースし,伝送レートが18Gbpsに高速化され,4K2K@60Hz, 21:9ディスプレイ,32CHオーディオ対応等,HDR(High Dynamic Rate)対応等,様々な機能が追加された.
DisplayPortはVGAやDVIに替わるパソコンの次世代インターフェースとして普及が始まっており,超高解像度での利用を視野に入れて2014/9にバージョン1.3がリリースされ,8K4Kをターゲットとして伝送レートが 従来比1.5倍の32.4Gbpsとなり,ディスプレイ・インターフェースとしては最高速のバンド幅が確保されている.さらにUSB-Type-C,Adaptive-Syncなど,ユニークな機能がサポートされた.しかもDisplayPort では,eDPやMyDP,iDPなどファミリ規格が充実していることが特徴である.
また,機器内のビデオインターフェースもその用途に合わせた技術が盛り込まれており,特に液晶ディスプレイは,機器内ビデオ・インターフェースの代表例である.
HDMI,DisplayPortとも規格の理解,開発のポイントを知りたいという要望が多くよせられており,本セミナでは,外部機器間ディスプレイ・インターフェースであるHDMI,DisplayPort,および機器内で使われる高速ビデオ・インターフェースについて,その概要と開発のポイントを解説する.さらに高速インターフェースの回路設計技術についても触れ,物理層の動作原理について詳しく解説する.
※ 本セミナは,実験実演および機材の提供に関してテクトロニクス様のご協力をいただいています.
※ 本セミナは,「HDMI & DisplayPort規格の基礎とディスプレイ・インターフェース開発の実際」を改題,リニューアルした講座です.
DisplayPortはVGAやDVIに替わるパソコンの次世代インターフェースとして普及が始まっており,超高解像度での利用を視野に入れて2014/9にバージョン1.3がリリースされ,8K4Kをターゲットとして伝送レートが 従来比1.5倍の32.4Gbpsとなり,ディスプレイ・インターフェースとしては最高速のバンド幅が確保されている.さらにUSB-Type-C,Adaptive-Syncなど,ユニークな機能がサポートされた.しかもDisplayPort では,eDPやMyDP,iDPなどファミリ規格が充実していることが特徴である.
また,機器内のビデオインターフェースもその用途に合わせた技術が盛り込まれており,特に液晶ディスプレイは,機器内ビデオ・インターフェースの代表例である.
HDMI,DisplayPortとも規格の理解,開発のポイントを知りたいという要望が多くよせられており,本セミナでは,外部機器間ディスプレイ・インターフェースであるHDMI,DisplayPort,および機器内で使われる高速ビデオ・インターフェースについて,その概要と開発のポイントを解説する.さらに高速インターフェースの回路設計技術についても触れ,物理層の動作原理について詳しく解説する.
※ 本セミナは,実験実演および機材の提供に関してテクトロニクス様のご協力をいただいています.
※ 本セミナは,「HDMI & DisplayPort規格の基礎とディスプレイ・インターフェース開発の実際」を改題,リニューアルした講座です.
1.高速ビデオ・インターフェースの登場と規格
1.1 パラレル・インターフェースからシリアル・インターフェースへ
1.2 シリアル・インターフェース化による利点
1.3 高速シリアル・インターフェースの規格
2.DVIとHDMIの基本技術
2.1 DVIの成り立ち
2.2 DVIの特徴
2.3 DVIの物理層
2.4 HDMIの成り立ち
2.5 HDMIの基本技術
2.6 HDMIとDVIの比較
3.HDMI1.3/1.4で追加された機能
3.1 HDMI1.3で追加された機能
3.2 HDMI1.4で追加された機能
4.HDMI2.0/2.0aで追加された機能
4.1 HDMIのハードウェア構成
4.2 今後のHDMIに求められる機能
4.3 評価装置を使った実演
5.DisplayPortの基本技術
5.1 DisplayPortの成り立ち
5.2 VESAコンソーシアム
5.3 DisplayPortの特徴
5.4 高速伝送を実現するための回路技術
5.5 DisplayPortのリンク層の構成
5.6 DisplayPortの物理層の構成
5.7 AUX-CHの機能
5.8 DisplayPort1.2で追加された機能
5.9 DisplayPort1.3で追加された機能
5.10 DisplayPortとレガシ・インターフェースとの接続
5.11 評価装置を使った実演
6.DisplayPort1.3で追加された機能
6.1 HBR3と84K4対応
6.2 DP-ALT-Mode対応(USB-TypeC)
6.3 Adaptive-Sync対応
7.HDMIとDisplayPortの比較
7.1 HDMIとDisplayPortの位置づけ
7.2 HDMIとDisplayPortの対比
8.機器内高速ビデオ・インターフェース
8.1 デジタル・テレビの内部インターフェース
8.2 液晶パネルの駆動方法
8.3 液晶テレビの内部インターフェース
8.4 iDP(internal DisplayPort)
8.5 miniLVDS
8.6 ノート・パソコン内部インターフェース
8.7 eDP(Embedded DisplayPort)
8.8 ポストminiLVDSインターフェース
8.9 モバイル系高速ディスプレイ・インターフェースMyDP
8.10 DisplayPortファミリ規格の比較
8.11 評価装置を使った実演
9.高速ビデオ・インターフェースの相互接続性
9.1 高速ディスプレイ・インターフェースの相互接続問題
9.2 映像が出ないケース
9.3 Sink機器が信号を誤判定するケース
9.4 画質が問題(表示がおかしい)になるケース
9.5 画質問題(画面にノイズが出るケース)
9.6 音声が出ないケース
9.7 音声にノイズが出るケース
9.8 HDCPエラーが発生するケース
9.9 デバッグ・アプローチ
10.高速ビデオ・インターフェースのシステム動作
10.1 HDMIのシステム動作
10.2 DisplayPortのシステム動作
10.3 コンプライアンス・テストとプラグ・フェスタ
10.4 高速ディスプレイ・インターフェースの評価
10.5 伝送路の評価項目
10.6 評価装置を使ったシミュレーション環境の実演
11.高速ディスプレイ・インターフェースのデバイス設計
11.1 高速差動信号の特長
11.2 最適な回路技術を選択
11.3 差動増幅回路の基本動作
11.4 LVDSの回路設計技術
11.5 HDMIの回路設計技術
11.6 DisplayPortの回路設計技術
※ 上記講義の途中で3か所,高速インターフェースの測定実演,計測のポイント・デモを行います.
●対象聴講者
・HDMIやDisplayPortなどの高速ディスプレイ・インターフェースの開発エンジニア
・最新のディスプレイ・インターフェースの動向に興味のある開発エンジニア
●講演の目標
・HDMI,DisplayPortをはじめとする高速ディスプレイ・インターフェースの概要,および開発のポイントが分かる
●使用するテキスト
長野 英生;『高速ビデオ・インターフェース--HDMI&DisplayPortのすべて』,CQ出版社,2013年8月.

●受講者が持参するもの
・テキスト:書籍『高速ビデオ・インターフェース--HDMI&DisplayPortのすべて』,定価4,536円(税込)をご持参ください.
※ テキストは当日,セミナ会場でもお買いお求めいただけますが,セミナの内容の理解を深めるためにも,ぜひ,事前に購読してセミナに参加されることを強くお勧めします.
●参考文献
長野 英生;『最新ビデオ規格 HDMI & DisplayPort』,Interface,2013年4月号 別冊付録.
1.1 パラレル・インターフェースからシリアル・インターフェースへ
1.2 シリアル・インターフェース化による利点
1.3 高速シリアル・インターフェースの規格
2.DVIとHDMIの基本技術
2.1 DVIの成り立ち
2.2 DVIの特徴
2.3 DVIの物理層
2.4 HDMIの成り立ち
2.5 HDMIの基本技術
2.6 HDMIとDVIの比較
3.HDMI1.3/1.4で追加された機能
3.1 HDMI1.3で追加された機能
3.2 HDMI1.4で追加された機能
4.HDMI2.0/2.0aで追加された機能
4.1 HDMIのハードウェア構成
4.2 今後のHDMIに求められる機能
4.3 評価装置を使った実演
5.DisplayPortの基本技術
5.1 DisplayPortの成り立ち
5.2 VESAコンソーシアム
5.3 DisplayPortの特徴
5.4 高速伝送を実現するための回路技術
5.5 DisplayPortのリンク層の構成
5.6 DisplayPortの物理層の構成
5.7 AUX-CHの機能
5.8 DisplayPort1.2で追加された機能
5.9 DisplayPort1.3で追加された機能
5.10 DisplayPortとレガシ・インターフェースとの接続
5.11 評価装置を使った実演
6.DisplayPort1.3で追加された機能
6.1 HBR3と84K4対応
6.2 DP-ALT-Mode対応(USB-TypeC)
6.3 Adaptive-Sync対応
7.HDMIとDisplayPortの比較
7.1 HDMIとDisplayPortの位置づけ
7.2 HDMIとDisplayPortの対比
8.機器内高速ビデオ・インターフェース
8.1 デジタル・テレビの内部インターフェース
8.2 液晶パネルの駆動方法
8.3 液晶テレビの内部インターフェース
8.4 iDP(internal DisplayPort)
8.5 miniLVDS
8.6 ノート・パソコン内部インターフェース
8.7 eDP(Embedded DisplayPort)
8.8 ポストminiLVDSインターフェース
8.9 モバイル系高速ディスプレイ・インターフェースMyDP
8.10 DisplayPortファミリ規格の比較
8.11 評価装置を使った実演
9.高速ビデオ・インターフェースの相互接続性
9.1 高速ディスプレイ・インターフェースの相互接続問題
9.2 映像が出ないケース
9.3 Sink機器が信号を誤判定するケース
9.4 画質が問題(表示がおかしい)になるケース
9.5 画質問題(画面にノイズが出るケース)
9.6 音声が出ないケース
9.7 音声にノイズが出るケース
9.8 HDCPエラーが発生するケース
9.9 デバッグ・アプローチ
10.高速ビデオ・インターフェースのシステム動作
10.1 HDMIのシステム動作
10.2 DisplayPortのシステム動作
10.3 コンプライアンス・テストとプラグ・フェスタ
10.4 高速ディスプレイ・インターフェースの評価
10.5 伝送路の評価項目
10.6 評価装置を使ったシミュレーション環境の実演
11.高速ディスプレイ・インターフェースのデバイス設計
11.1 高速差動信号の特長
11.2 最適な回路技術を選択
11.3 差動増幅回路の基本動作
11.4 LVDSの回路設計技術
11.5 HDMIの回路設計技術
11.6 DisplayPortの回路設計技術
※ 上記講義の途中で3か所,高速インターフェースの測定実演,計測のポイント・デモを行います.
●対象聴講者
・HDMIやDisplayPortなどの高速ディスプレイ・インターフェースの開発エンジニア
・最新のディスプレイ・インターフェースの動向に興味のある開発エンジニア
●講演の目標
・HDMI,DisplayPortをはじめとする高速ディスプレイ・インターフェースの概要,および開発のポイントが分かる
●使用するテキスト
長野 英生;『高速ビデオ・インターフェース--HDMI&DisplayPortのすべて』,CQ出版社,2013年8月.

●受講者が持参するもの
・テキスト:書籍『高速ビデオ・インターフェース--HDMI&DisplayPortのすべて』,定価4,536円(税込)をご持参ください.
※ テキストは当日,セミナ会場でもお買いお求めいただけますが,セミナの内容の理解を深めるためにも,ぜひ,事前に購読してセミナに参加されることを強くお勧めします.
●参考文献
長野 英生;『最新ビデオ規格 HDMI & DisplayPort』,Interface,2013年4月号 別冊付録.
【講師】
長野 英生 氏〔株式会社セレブレクス 〕
1992年 同志社大学工学部卒。同年 三菱電機株式会社入社。 2010 年に三菱電機株式会社、株式会社日立製作所、日本電気株式会社の半導体事業の統合によりルネサス エレクトロニクス株式会社に転籍。2015 年から半導体ベンチャの株式会社セレブレクス。一貫してディスプレイ用LSI の開発、高速インターフェースの技術開発、コンソーシアム活動に従事。高速インターフェース関連、CMOS アナログ設計関連の講演、特許出願多数。 著書に、「高速ビデオ・インターフェースHDMI & DisplayPort のすべて」(CQ 出版社)、「ディジタル画像技術事典200」(同)、「USB Type-C のすべて」(同)、「Interface 別冊付録 最新ビデオ規格HDMI とDisplayPort」(同), 「LTspiceで解析 CMOS回路入門」(同)。他に月刊誌「Interface」(同)や「FPGA マガジン」(同)に、高速ビデオ信号関連の最新動向を寄稿。VESA(Video Electronics Standard Association)Japan Task Group 所属。
長野 英生 氏〔株式会社セレブレクス 〕
1992年 同志社大学工学部卒。同年 三菱電機株式会社入社。 2010 年に三菱電機株式会社、株式会社日立製作所、日本電気株式会社の半導体事業の統合によりルネサス エレクトロニクス株式会社に転籍。2015 年から半導体ベンチャの株式会社セレブレクス。一貫してディスプレイ用LSI の開発、高速インターフェースの技術開発、コンソーシアム活動に従事。高速インターフェース関連、CMOS アナログ設計関連の講演、特許出願多数。 著書に、「高速ビデオ・インターフェースHDMI & DisplayPort のすべて」(CQ 出版社)、「ディジタル画像技術事典200」(同)、「USB Type-C のすべて」(同)、「Interface 別冊付録 最新ビデオ規格HDMI とDisplayPort」(同), 「LTspiceで解析 CMOS回路入門」(同)。他に月刊誌「Interface」(同)や「FPGA マガジン」(同)に、高速ビデオ信号関連の最新動向を寄稿。VESA(Video Electronics Standard Association)Japan Task Group 所属。